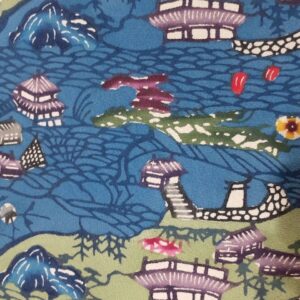究極の単衣御召「五百機織(いおはたおり)」の歴史、現在、製法、特徴の話

大正12年創業、新宿・甲州屋呉服店の三代目社長、 志村 賢三(シムラ ケンゾウ)です。

今回のコラムでは、究極の単衣御召「五百機織(いおはたおり)」の歴史、現在、製法、特徴などを解説いたします。

江戸時代後期まで、高級織物の独壇場であった西陣織の世界。
明治維新、続く幕府崩壊によって、将軍家をはじめ武家階級の需要が消滅、さらに東京遷都により、貴族や御用商人も東京へと移り住むに至りました。
それに伴い、千年の都の大いなる需要が消失。
京都経済全体が消沈を余儀なくされました。
こうした状況の中、それまでは高級西陣織は空引機が主流でしたが、明治5年、西陣代表者がフランスのリヨンに渡り、ジャガードの技術を大いに学び、ジャガード(※)、バッタン、金筬、紋織機など10種の様式機織器を持ち帰りました。
(代表団:佐倉常七、吉田忠七、井上伊兵衛)
※ジャガードは、江戸時代の空引機の空引きに変わる紋織の装置で、意匠図に従って穴をあけた紋紙を一枚ずつ移動させることで経糸開口の操作をする装置で、織機の上に取り付けるもの。
続いて明治6年、伊達弥助がオーストリア、イギリス万博へ渡欧。
オーストリアのジャガードや、1200点に及ぶ各国の見本裂帳などを持ち帰りました。
先に佐倉らの持ち帰ったジャガードは、明治7年3月開催の第3回京都博覧会に出品公開され、模範品の製織、伝習生への技術伝承がなされました。
明治13年に国産ジャガードが完成し、製織に成功。
従来の空引き機とジャガードで「すみ分け」の時代が到来し、手仕事回帰への重要な役割も果たしつつ、同時にさらなる技術の追求を図っていきました。
その後、明治23年竣工の皇居装飾用織物の受注により、国産ジャガードが大きく普及していく契機となります。
(インテリア部門参入への先駆けにもなる)
ジャガードの技術は桐生に全面的に伝わり、桐生などから有能な職人が米沢に来米し、時の経過とともその技術が伝承されたことに加え、京都との歴史的つながりをよりどころとして極めて、高い完成度をもって受け継がれてきたのでした。
米沢織の技術は小千谷によるところが大きいですが、その一方、西陣織の技術も極めて精確に伝承されたのです。
山形県は多雨多湿で、山の周辺は豪雪地となる気候特性を持つため、導入された技術を生かして、かつては地域で40軒以上もの織屋で雨コートが織られていましたが、現在は「佐志め織物」唯一軒のみとなりました。
「佐志め織物」は、現四代目亨定氏の曾祖母・佐藤志め氏により、大正13年に創業。
主力商品の一つである雨コート地「天平錦」を織りながら、この度ひもとく「五百機織(いおはたおり)」の単衣御召を作品化しています。
デジタル技術が発達し、コンピューターグラフィックスで製紋したデータを使っている織屋が多い中、今なお、そしてこれからもジャガード織機で紋紙を使って製織を続けていくことに徹しています。
(柄数が多いと、2000枚以上もの紋紙を使用することもあります)
経糸に60デニール(21中三本駒撚り)という極細糸を4000本使用して織っていきます。
緯糸は強撚糸をしっかり打ち込みますが、撚りのかけ方に変化をつけて、糸自体に凹凸感があることから、肌に当たっても快適で、サラサラした風合いを特徴としています。
(緯に濃く見える部分は、紬糸を入れて変化をもたせ、経に見えかくれする透かしを用いて清涼感を醸し出しています)
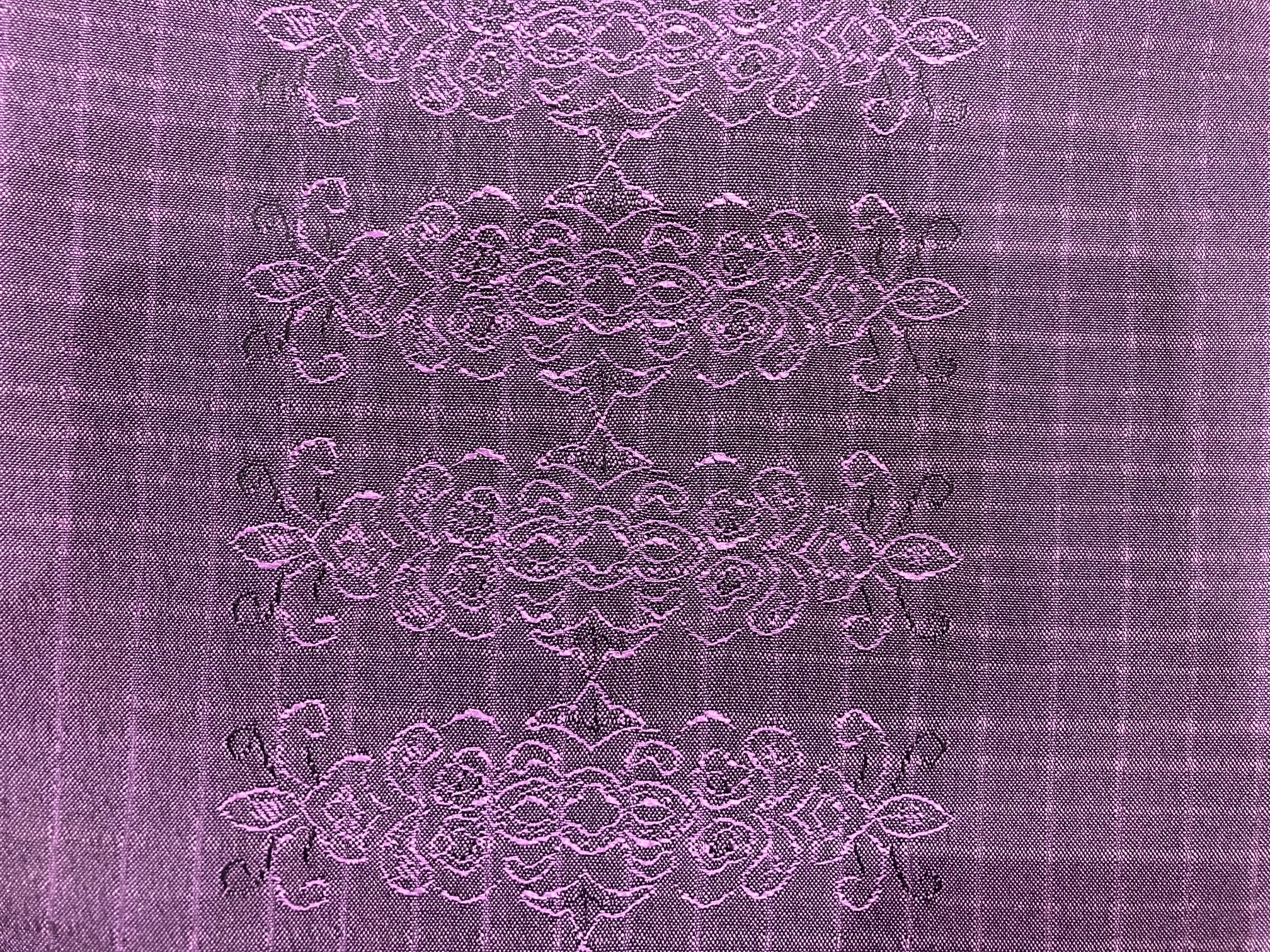
絽でも紗でもなく、春先から夏、秋の終わりまで着用することができます。
スリーシーズン単衣御召がこうして生まれたのです。
一口メモ
フランス革命の余韻が色濃く残る中、リヨンの工場で職人として日常を送るかたわら、発明家としてのジャカールは、織機の改善・改良に尽力。
1801年、パリの産業博覧会に織機を出品し、高い評価を得ることができた。
これがジャガードの始まりである。
手織職人らの失業への不安から、打ちこわしなどの大変な状況も乗り越え、数年を経てフランス国内だけでも約11,000台が使用されるに至った。
新宿・甲州屋呉服店について

当店甲州屋呉服店は、大正12年、新宿の地で創業しました。
和服好きの方や、着物のことでお困りの方に、“老舗の知恵” と “最適な(時には斬新な)方法” で、販売のみならず、お手入れ、着付け、レンタル、お預り等、あらゆる方法の中からピッタリなご提案をしています。
当店にて「五百機織(いおはたおり)」の単衣御召を取り扱っておりますので、ぜひお気軽にお越しくださいませ。

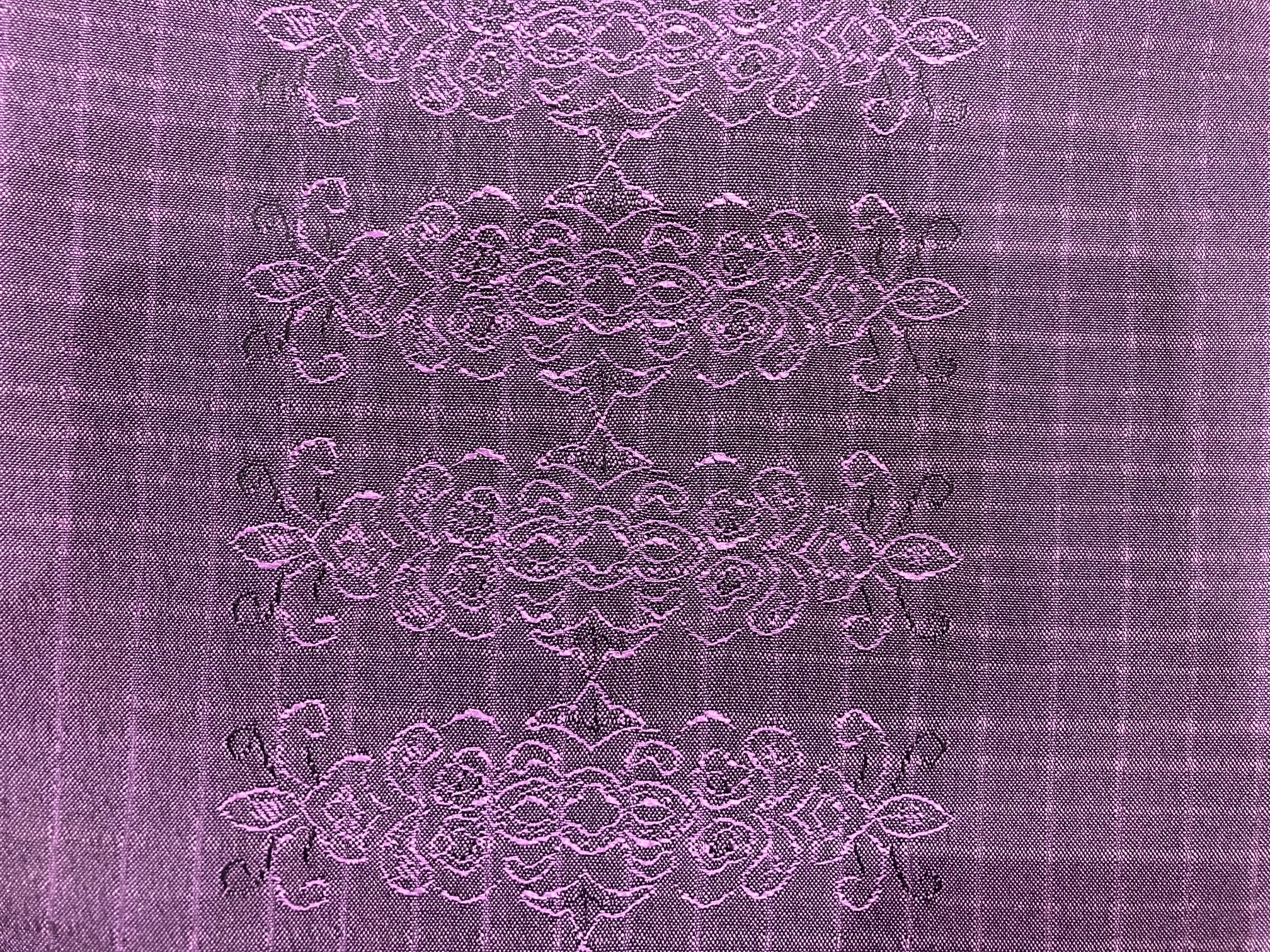

↓ ↓ ↓
【新宿・甲州屋呉服店の店舗案内はこちら】